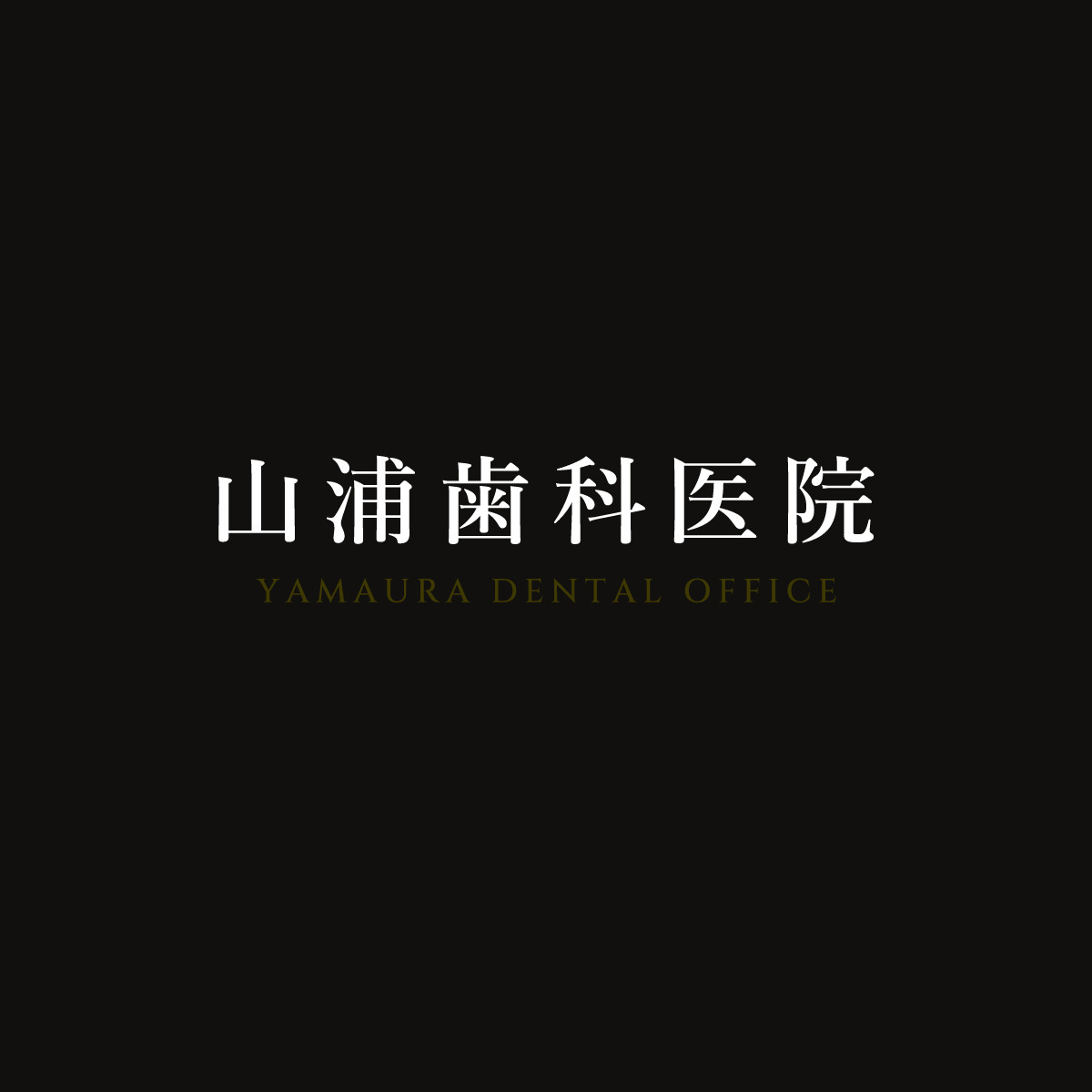知覚過敏の症状は?原因と治し方・予防法を現役の歯科医師が解説。
- 山浦 泰明

- 2025年9月2日
- 読了時間: 14分
更新日:2025年11月20日

冷たいアイスを食べた時や、冷たい飲み物を口に含んだ瞬間、歯がキーンとしみて思わず顔をしかめてしまった経験はありませんか?
このような症状は、多くの方が経験する「知覚過敏」かもしれません。
知覚過敏は虫歯ではないのに歯がしみる症状で、症状が進行すると、場合によっては日常生活にも支障をきたすこともあります。
この記事では、知覚過敏の症状から原因、治療法、予防法まで、山梨県甲府市の山浦歯科医院の院長が、現役歯科医師の立場から詳しく解説いたします。
知覚過敏とは?
知覚過敏とは、歯ブラシの毛先が触れたり、冷たい飲食物、甘いもの、風にあたった時などに歯に感じる一過性の痛みで、特に虫歯や歯の神経(歯髄)の炎症などの病変がない場合にみられる症状を指します。
医学的には「象牙質知覚過敏症」とも呼ばれます。
痛みの程度は個人差があり、軽い違和感程度から日常生活に支障をきたすほどの激痛まで様々ですが、痛みは「一過性」で、刺激を受けた瞬間は鋭い痛みを感じますが、長くても1分以内で消失します。
また、虫歯による痛みとは異なり、何もしていない時には痛みを感じないことが多いです。
知覚過敏の発生メカニズム
知覚過敏がなぜ起こるのかを理解するためには、歯の構造を知ることが大切です。
歯は歯茎から出ている部分は、外側から順に、エナメル質、象牙質、歯髄(神経)の3層構造になっていて、通常、歯の表面を覆うエナメル質は非常に硬く、外部からの刺激をブロックする役割を果たしています。
また、歯肉に埋まっている根の方はエナメル質が無く、象牙質、歯髄(神経)の2層構造になっています。
しかし、何らかの原因でエナメル質が剥がれたり、歯茎が下がって歯の根が露出したりすると、象牙質が外部にさらされます。
象牙質には「象牙細管」と呼ばれる無数の微細な管が存在し、これらは歯の神経まで通じています。
つまり、象牙質が露出してしまうと、冷たいものや熱いものなどの温度刺激や、歯ブラシの時など擦過刺激が象牙細管を通って直接神経に伝わり、痛みとして知覚過敏の症状が現れるようになります。
知覚過敏の主な症状
知覚過敏の症状は人によって様々ですが、以下のような場面で歯がしみる・痛むことが典型的です。
冷たい飲み物や食べ物(アイスクリーム、冷水など)で歯がしみる
熱い飲み物や食べ物(お茶、スープなど)で歯がしみる
甘いもの(チョコレート、ケーキなど)を食べた時に歯がしみる
酸っぱいもの(柑橘類、酢の物など)で歯がしみる
歯磨きの時、特に歯ブラシが当たると痛む
冷たい風が歯に当たると痛む
うがいをする時に水がしみる
これらの症状は、刺激を受けた瞬間にキーンとした鋭い痛みとして現れ、刺激がなくなればすぐに痛みも消えます。
痛みの程度は軽度から重度まで個人差があり、症状が進行すると日常生活に支障をきたすこともあります。
虫歯と知覚過敏の痛みの違い
項目 | 虫歯 | 知覚過敏 |
痛みのきっかけ | 何もしなくても痛むことが多い | 冷たい・熱い・甘い・歯ブラシなど特定の刺激 |
痛みの長さ | 長く続く | 数秒〜数十秒でおさまる |
痛みの質 | ズキズキ・鈍い痛み | キーンと鋭い痛み |
見た目の変化 | 黒や茶色の穴や変色が多い | 目立った変化は少ない(歯茎下がりなど) |
自然治癒 | しない | セルフケアで治る(軽度の場合) |
虫歯は、歯の表面のエナメル質から徐々に内部の象牙質、そして神経に向かって細菌感染が進行していく病気です。
初期は何も感じませんが、進行すると時々しみるような痛みがでて、さらに進行すると何もしていなくてもズキズキとした痛みが持続します。
進行した虫歯の場合は特に夜間や食事後に痛みが強く出やすく、自然に治ることはなく、放置すると悪化して歯の神経の治療や、ひどい場合には抜歯が必要になることもあります。外見的には黒や茶色の小さな穴や変色が見られることが多いです。
一方、知覚過敏は、歯のエナメル質がすり減ったり、歯茎が下がって象牙質が露出することで、冷たい飲み物や甘いもの、歯磨き時など特定の刺激に対して一時的に鋭い「キーン」とした痛みが走る症状です。
痛みは数秒〜数十秒程度で治まるのが特徴で、見た目に大きな変化がない場合も多く、軽度であれば専用歯磨き粉やブラッシング改善で症状が緩和することもあります。
知覚過敏の主な原因7つ
知覚過敏の原因は多岐にわたりますが、主に以下の7つが挙げられます。
1. 加齢による歯肉退縮(歯茎の下がり)
歯肉の位置は加齢とともに少しずつ下がってきますが、40代以降で特に顕著になります。
歯根部分の象牙質は、歯冠部よりも薄く、刺激に対してより敏感です。歯肉が下がることで、本来歯肉に覆われていた歯根部分が露出し、エナメル質のない象牙質がむき出しになり刺激に対して痛みが出るようになります。
加齢による歯肉退縮は自然なことのため、完全に防ぐことは難しいですが、歯科医院の定期検診や適切なセルフケアによって進行を遅らせることは可能です。
2. 誤った歯磨き方法
力を入れすぎた歯磨きや、硬い歯ブラシの使用は、歯肉を傷つけ下げる原因となります。
特に、横に大きくゴシゴシと磨く習慣がある方は要注意で、このような磨き方を続けると、露出した歯の根元の象牙質がくさび状に削れる「くさび状欠損」を引き起こします。
また、研磨剤の多い歯磨き粉を長期間使用することも、歯質を薄くする原因となります。
推奨している歯磨き方法は、歯ブラシを45度の角度で歯と歯肉の境目に当て、小刻みに動かし磨くバス法というブラッシング方法です。力は軽く、鉛筆を持つような握り方で行うのが理想的です。
3. 歯ぎしり・食いしばり
睡眠中の歯ぎしりや日中の食いしばりは、歯に過度な負担をかけ、エナメル質を摩耗させる大きな原因となります。
歯ぎしりによる力は、通常の噛む力の数倍にも達することがあり、歯の表面を削り取ってしまうほか、歯に亀裂が入ることもあり、そこから刺激が伝わりやすくなります。
歯ぎしりの原因は、ストレスなどが考えられ、無意識に行われるため自分では気づきにくいですが、もし家族から指摘されたり、朝起きた時に顎が疲れている、歯が痛いなどの症状がある場合は、歯ぎしりをしている可能性があるため、特に注意しましょう。
4. 酸蝕症(さんしょくしょう)による歯の溶解
現代の食生活では、炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢など、酸性の飲食物を摂取する機会が増えています。
エナメル質はpH5.5程度で、また露出した象牙質はpH6.0-6.2溶け始めます。
これらの酸性飲食物を頻繁に摂取すると、歯が徐々に溶けて薄くなる「酸蝕症」を引き起こします。
特に、炭酸飲料をちびちびと長時間かけて飲む習慣や、就寝前に酸性飲料を飲む習慣は危険です。
象牙質は弱い酸でも溶けやすいため、知覚過敏の症状が急速に進行することがあります。
5. 歯周病による影響
歯周病は、歯を支える歯肉や骨が炎症を起こす病気で、進行すると歯肉が下がり、歯根が露出します。
歯周病による歯肉退縮は、加齢による自然な退縮よりも急速に進行することが多く、より広範囲の象牙質露出を引き起こします。
また、歯周病の治療で歯石を除去した後は、それまで歯石に覆われていた部分が露出するため、一時的に知覚過敏の症状が強くなることがあります。
しかし、歯周病を放置すると最終的には歯を失うことになるため、適切な治療を受けることが重要です。
6. 歯の破折や亀裂
スポーツや事故による外傷、硬いものを噛んだ時の衝撃などで歯が破折したり、亀裂が入ることがあります。
歯の破折により象牙質が露出すると、知覚過敏の症状が現れます。
また、目に見えない微細な亀裂が入っている場合もあり、その場合も刺激が伝わりやすくなるため、破折や亀裂は放置せず、早期に歯科医院で相談し場合によっては治療することが必要です。
7. ホワイトニングの副作用
歯を白くするホワイトニング治療は、一時的に知覚過敏を引き起こすことがあります。
これはホワイトニング剤に含まれる成分が歯に浸透し、一時的に歯の神経を刺激するためです。
多くの場合、ホワイトニング終了後数日から1週間程度で症状は改善しますが、もともと知覚過敏がある方は症状が強く出ることがあるため、不安な場合は事前に歯科医師に相談することが大切です。

歯科医院での知覚過敏の治療法
上記の通り、知覚過敏の原因は様々あるため、原因ごとにどの治療方法をすべきかも変わります。
ここでは代表的な歯科医院の治療方法を原因別に紹介します。
薬剤塗布による治療
歯科医院では、知覚過敏の症状を緩和するために様々な薬剤を使用します。
薬剤塗布は即効性が少ないため、薬剤の複数回の塗布が必要なことがあります。
コーティング材・詰め物による保護
象牙質の露出が広範囲にわたる場合や、歯の根元が大きく削れている場合は、コーティング材や詰め物で物理的に保護する治療を行います。
歯科用の接着材を用いて、薄い樹脂の膜で象牙質表面を覆うことで、外部刺激を遮断します。
くさび状欠損などで歯が凹んでいる場合は、コンポジットレジン(歯科用プラスチック)で形態を回復させながら象牙質を保護します。
マウスピース(ナイトガード)
歯ぎしりや食いしばりが原因の知覚過敏には、マウスピース(ナイトガード)の使用が効果的です。
就寝時に装着することで、歯ぎしりによる歯の摩耗や歯への過度な負担を防ぎます。
マウスピースは患者様の歯型に合わせてオーダーメイドで作製され、違和感なく装着できるよう調整します。
保険適用で作製可能で、3割負担の場合3,000円から4,000円程度で作ることができます。
使用を続けることで、知覚過敏の進行を防ぐだけでなく、顎関節症の予防にもつながります。
レーザー治療
近年、知覚過敏の治療にレーザーを使用する方法が注目されています。
レーザー照射による治療は露出した象牙細管を封鎖し、神経の過敏性を低下させることができ、痛みがなく、短時間で処置が完了するため、患者様の負担が少ないのが特徴です。
また、レーザーには殺菌効果もあるため、歯周病を併発している場合にも有効とされています。
根管治療(症状が重い場合)
知覚過敏の症状が非常に激しく、日常生活に支障をきたす場合や、他の治療法で改善が見られない場合は、最終手段として根管治療(神経を取る治療)を検討することがあります。
歯の神経を取り除くことで、痛みを感じなくなりますが、歯が脆くなるなどのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
山浦歯科医院では、できる限り歯の神経を保存する治療を心がけていますが、希望される場合や、治療が必要と判断した場合、高精度で安全に行える精密根管治療の処置を行います。
自宅でできる知覚過敏の対処法
軽度の知覚過敏の場合、自宅でのセルフケアで対処できるケースもあります。
以下では、自宅でできる代表的なセルフケア方法です。
1.知覚過敏用歯磨き粉を活用する
「シュミテクト」などに代表される市販の知覚過敏用歯磨き粉は、手軽に始められる対処法として多くの方に利用されています。
こういった歯磨き粉には硝酸カリウムという成分が配合されており、この成分があると露出した象牙細管をカバーし、神経への刺激伝達を抑制する効果があります。
知覚過敏用歯磨き粉のポイントは継続的に使うことで、通常、1〜2週間程度使い続けることで効果を実感できることが多いですが、使用を中断すると症状が再発する可能性があります。
また、歯磨き後すぐにうがいをせず、少し口の中に留めておくことで、有効成分がより効果的に作用します。
ただし、2週間以上使用しても改善が見られない場合は、知覚過敏以外の原因も考えられるため、歯科医院での診察をおすすめします。
2.正しいブラッシングをする
知覚過敏の改善と予防には、正しいブラッシング方法の習得が不可欠です。
まず、歯ブラシは「やわらかめ」または「ふつう」の硬さを選びましょう。
歯ブラシの持ち方は、鉛筆を持つように軽く握り、力を入れすぎないことが大切です。
磨き方は、歯と歯肉の境目に歯ブラシを45度の角度で当て、小刻みに動かすバス法をお勧めしています。1本1本の歯を丁寧に、10〜20回程度磨くのが理想的です。
特に知覚過敏の症状がある部分はより優しく磨くよう心がけましょう。
3.食生活の改善
知覚過敏の症状を改善するためには、食生活の見直しも重要です。
酸性の飲食物は、できるだけ控えめにしましょう。炭酸飲料、スポーツドリンク、柑橘類、酢の物などを摂取する際は、以下の点に注意が必要です。
酸性の飲食物を摂取した後は、30分以上経ってから歯磨きをする
酸性飲料を飲んだ後は、水でうがいをして口内を中和する
これらの対策により、酸性の飲食物からの影響を減らすことができます。
4.よく噛んで唾液の分泌を促進する
唾液には、口腔内のpHを中和し、唾液中に含まれるカルシウムやリンにより歯の再石灰化を促進する重要な役割があります。
また、軽度に脱灰した歯の表面を修復し、知覚過敏の症状を和らげる効果もあります。
唾液の分泌を促進するためには、よく噛んで食事をすること、ガムを噛むこと(キシリトール配合のものが望ましい)、こまめな水分補給などが効果的です。
また、口呼吸は口腔内を乾燥させ、唾液の効果を低下させるため、鼻呼吸を心がけることも大切です。
知覚過敏の予防方法
最後に知覚過敏の予防方法についても紹介します。
定期的な歯科検診
知覚過敏の予防には、定期的な歯科検診が欠かせません。
歯科検診では、歯や歯肉の状態をチェックし、知覚過敏の原因となる歯周病や咬み合わせの問題などを早期に発見できます。
また、プロフェッショナルクリーニングにより、自分では除去できない歯石や着色を取り除き、口腔内環境を改善でき、知覚過敏だけでなく、虫歯や歯周病の予防にもつながるため、歯の健康を維持する上で最も重要な習慣といえます。
ストレス管理と生活習慣の改善
歯ぎしりや食いしばりの主な原因はストレスです。
日常生活でのストレス管理は、知覚過敏の予防に大きく貢献しますので適度な運動、十分な睡眠、趣味の時間を持つなど、リラックスできる時間を意識的に作ることが大切です。
また、日中の食いしばりに気づいたら、意識的に歯を離し、顎の力を抜くよう心がけましょう。
デスクワークの際は、定期的に休憩を取り、首や肩のストレッチを行うことで、顎周りの緊張を和らげることができます。
フッ素の活用による歯質強化
フッ素は、歯の再石灰化を促進し、エナメル質を強化する効果があります。
フッ素配合歯磨き粉の使用はもちろん、歯科医院でのフッ素塗布も効果的です。
特に高濃度フッ素配合の歯磨き粉(1,450ppm)は、成人の知覚過敏予防に有効とされています。
また、フッ素洗口液を就寝前に使用することで、睡眠中の唾液分泌低下時にも歯を保護できるためおすすめです。
適切な口腔ケア用品の選び方
知覚過敏の予防には、適切な口腔ケア用品の選択も重要です。
歯ブラシは、やわらかめのものを選び、電動歯ブラシを使用する場合は、圧力センサー付きのものがおすすめです。
歯磨き粉は、前述の通り研磨剤が少なく、フッ素配合のものが良いですが、知覚過敏用の歯磨き粉も予防効果があります。
また、デンタルフロスや歯間ブラシも重要で、歯と歯の間の清掃により、むし歯や歯周病の予防につながります。
知覚過敏の放置リスクと早期治療の重要性
知覚過敏を放置すると、初期は冷たいものだけにしみていた症状が、温かいものや甘いものにも反応するようになり、最終的には何もしなくても痛みを感じるようになることがあります。
痛みのために十分な歯磨きができなくなり、虫歯や歯周病のリスクが高まりまり、さらに知覚過敏が悪化するという悪循環に陥ります。
早期に適切な治療を受けることで、以下のようなメリットがあります。
簡単な治療で症状が改善する可能性が高い
治療費用を抑えることができる
歯の神経を温存できる可能性が高い
生活の質を維持できる
知覚過敏の症状を感じたら、「そのうち治るだろう」と放置せず、早めに歯科医院を受診することが大切です。
知覚過敏の治療は「山梨県甲府市の山浦歯科医院」
知覚過敏は、多くの方が経験する歯のトラブルですが、適切な対処により改善が可能です。
症状の原因は人それぞれ異なるため、まずは正確な診断を受けることが重要です。
日常生活では、正しい歯磨き方法の実践、知覚過敏用歯磨き粉の使用、食生活の見直しなど、自分でできる対策を継続することが大切ですが、自己判断での対処には限界があります。
症状が改善しない場合や悪化する場合は、速やかに歯科医院を受診してください。
山梨県甲府市の山浦歯科医院では、知覚過敏の診断から治療まで、最新の設備と技術を用いた包括的なアプローチを行っています。
手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を使用した精密な診査により、知覚過敏の原因を正確に特定し、患者様一人ひとりに最適な治療計画をご提案します。
また、治療後も定期的なメンテナンスを通じて、長期的な口腔健康の維持をサポートしていますので、知覚過敏でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個々の症状や治療については必ず歯科医師に相談し、適切な診断や治療を受けてください。