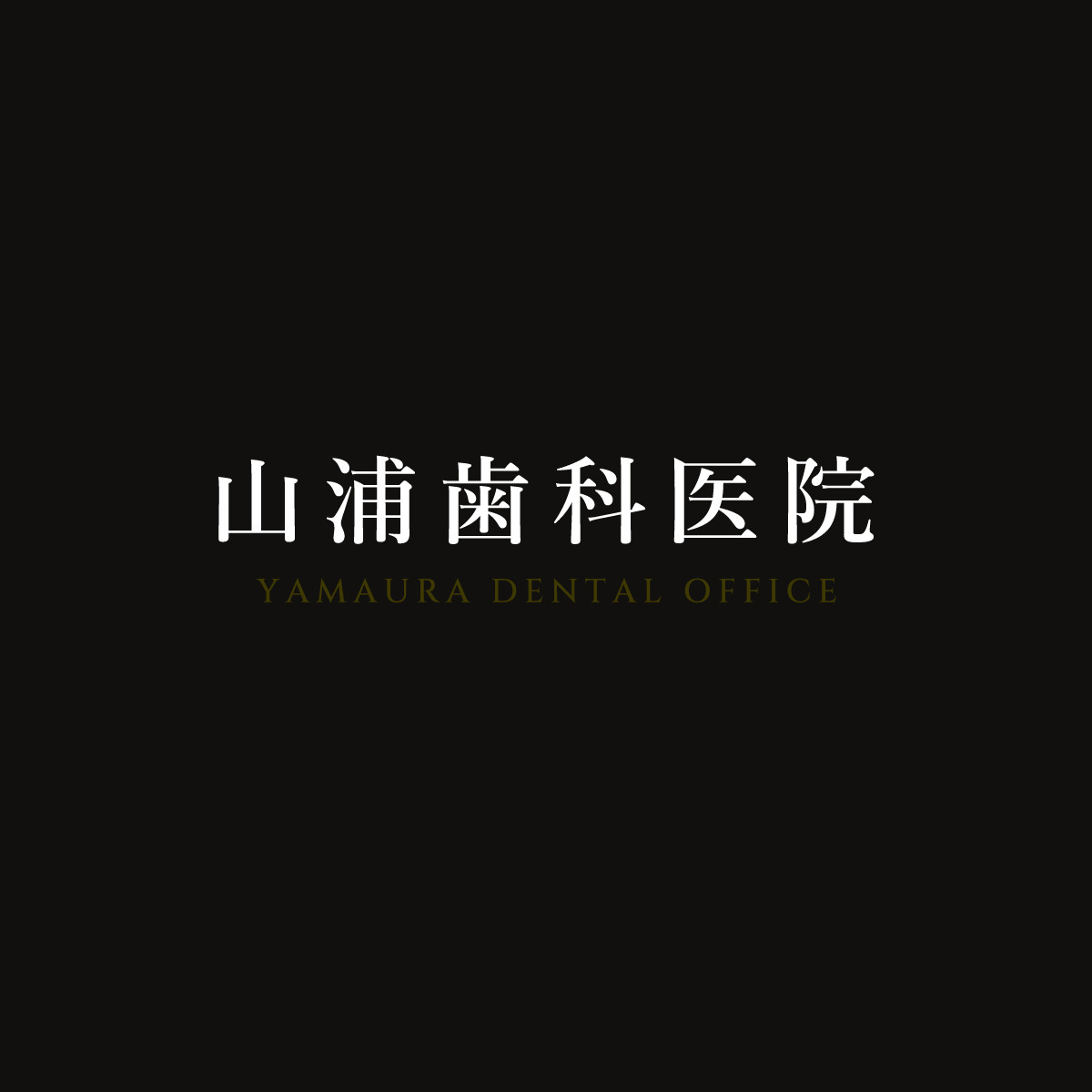歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏・歯周病は何が違う?歯周病専門医が違いを解説
- 山浦 泰明

- 2025年2月21日
- 読了時間: 6分
更新日:2025年11月20日

「歯肉炎」、「歯周炎」、「歯槽膿漏」、「歯周病」のそれぞれの用語の違いを知っていますか?
これらの言葉はすべて歯茎や歯を支える組織におきる病気ですが、実はそれぞれ指し示す状態や進行度合いが異なります。
本記事では、山梨県甲府市の山浦歯科医院の院長で、現役の歯周病専門医が、これら4つの言葉の違いを分かりやすく解説するとともに、それぞれの症状・原因・治療法についてご紹介していきます。
これらの言葉の意味がピンとこない方はぜひ参考にしてください。
歯周病とは?
まず大前提として「歯周病」という言葉は、歯を支えている歯肉(歯ぐき)・歯槽骨(しそうこつ)・歯根膜(しこんまく)などの“歯周組織”に起こる疾患の総称です。
日本では成人の8割以上が歯周病に罹患しているともいわれ、国民病とも呼ばれるほど非常に身近な病気です。
歯周病は大きく分けると、歯肉に炎症がとどまっている状態=「歯肉炎」と、歯を支える骨や組織にまで炎症が進行した状態=「歯周炎」に分類されます。
では、歯周炎と歯槽膿漏、そして一般的な「歯周病」の使われ方にはどのような違いがあるのでしょうか?
歯肉炎・歯周炎・歯槽膿漏・歯周病の意味と違い
ここでは、よく耳にする4つの言葉について、それぞれの意味を整理してみましょう。
歯肉炎(しにくえん)の意味
歯肉炎とは、その名の通り歯ぐき(歯肉)のみが炎症を起こした状態を指します。
プラーク(歯垢)の蓄積によって歯ぐきが腫れたり、歯磨き時に出血したりする症状が代表的です。
特徴
歯周ポケット(歯と歯肉の間の溝)は比較的浅い
歯槽骨はまだ破壊されていない、または軽度
痛みがほとんどない場合が多い
治療の難易度
この段階ではきちんとしたブラッシングや歯科クリニックでのクリーニングによって、比較的短期間で改善する可能性が高いです。
歯周炎(ししゅうえん)の意味
歯肉炎からさらに進行し、歯周組織(歯槽骨や歯根膜など)にまで炎症が及んだ状態を「歯周炎」と呼びます。
特徴
歯周ポケットが深くなり、歯槽骨が破壊され始める
歯ぐきの腫れや出血に加え、歯の動揺(ぐらつき)や知覚過敏が現れることもある
治療の難易度
歯肉炎よりも治療期間が長くなりやすく、専門的な処置(スケーリング・ルートプレーニングなど)が必須となります。
また、状態によっては外科的処置が求められるケースもあります。
歯槽膿漏(しそうのうろう)の意味
歯槽膿漏は昔から使われていた一般的な呼び方で、「膿が漏れる」という字が示すように、歯ぐきや歯周ポケットから膿が出るほど重症化した状態を表します。
日常的には歯周病と同じ意味で使われることがありますが、最近ではやや古い呼び方です。
特徴
歯茎から膿が出たり、口臭が強くなったりする
歯のぐらつきが顕著になり、最悪の場合は抜け落ちる
治療の難易度
かなり進行した状態であることが多いため、歯を保存するのが難しくなるケースもあるのが実情です。
歯周病(ししゅうびょう)の意味
歯周病は、歯肉炎と歯周炎を総称した言葉として、あるいは歯周炎を中心とした歯を支える組織の疾患全般を指す広い概念です。
日本歯周病学会では、歯周組織に生じる炎症性疾患をまとめて「歯周病」と呼んでいます。
特徴
虫歯(う蝕)とは異なり、比較的自覚症状が少ないまま進行する
日本人成人の多くが罹患しているといわれるほど身近な病気
使われ方
歯周病という言葉はメディアや医療情報でもよく用いられ、「歯ぐきの病気をまとめて示す一般名称」として認識されています。
本来は進行度に応じて歯肉炎・歯周炎と区別しますが、一般的にはまとめて歯周病と呼びます。
歯肉炎から歯周炎に進行するメカニズム
歯肉炎は歯ぐきに炎症が起こっている段階ですが、適切なケアを怠ると歯肉の下部、さらに歯槽骨や歯根膜にまで炎症が波及し、歯周炎へと進行します。
ステージ1.プラーク(歯垢)の蓄積
歯と歯ぐきの境目にプラーク(歯石)がたまり、細菌が繁殖します。
プラーク1mg中にはおよそ10億個の細菌がいるとも言われ、適切に除去しないと歯周組織に炎症を引き起こします。
ステージ2.歯石の形成
プラークが取り除かれないまま放置されると、唾液中のミネラルと結合して歯石となります。
歯石は表面がザラザラしており、細菌が付着しやすくなります。
一度歯石になってしまうとブラッシングでは落とせず、歯科医院での専門的な器具による除去が必要です。
ステージ3.歯周ポケットの深部化
炎症が続くと歯ぐきが腫れ、歯と歯肉の間の溝(歯周ポケット)が深くなります。
そこに細菌がさらに住みつきやすくなり、悪化のスパイラルに陥ります。
ステージ4.歯槽骨の破壊
歯周ポケットの奥に潜む細菌が毒素を出し、歯を支える骨が徐々に溶かされていきます。
やがて歯がぐらつき、重症の場合は抜歯に至るケースもあります。

歯周病(歯肉炎・歯周炎)の予防方法
歯周病を防ぐには、毎日のセルフケアと定期的な歯科医院でのチェックが欠かせません。
自宅での適切な歯磨き
歯周病予防の基本は、毎日の適切な歯磨きです。
歯ブラシを歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当て、優しく細かく動かして磨きましょう。
また、歯と歯の間の汚れはブラッシングだけでは落としきれませんので、デンタルフロスや歯間ブラシを併用すると、より効果的に歯垢を除去できます。
1日2〜3回の歯磨きを習慣づけるのがおすすめです。
食事の見直し
食事の内容も歯周病予防に影響します。
ビタミンCやカルシウムを多く含む食品(野菜、乳製品、魚)は、歯や歯ぐきを強く保ち、炎症を抑える働きがあります。
また、よく噛むことで唾液の分泌が促進され、口の中の細菌が洗い流されやすくなります。
バランスの取れた食生活を心がけ、歯周病のリスクを抑えましょう。
禁煙とストレス管理
タバコとストレスも歯周病の大きな要因です。
喫煙すると血流が悪くなり、歯ぐきの抵抗力が低下し、さらに免疫機能が低下することで、歯周病の進行が早まります。
また、ストレスも免疫力を低下させる要因になるため、適度な運動やリラックスできる時間を確保することも大切です。
定期的な歯科検診
歯周病は自覚症状が出にくいため、自宅でのセルフケアに加えて、歯科医院での定期的な歯科検診も行うことを推奨します。
歯科医院では、歯垢や歯石を除去する専用の器具や研磨剤を使ったクリーニングを行うため、自宅でのケアでは落としきれない汚れを除去でき、細菌の繁殖を防ぐことができます。
自宅でのセルフケアと定期的なメンテナンスを組み合わせることは非常に効果的です。
歯周病・歯周炎にお悩みなら山梨県甲府市の「山浦歯科医院」
もし少しでも「歯ぐきの腫れ」や「出血」「口臭の悪化」「歯のぐらつき」などが気になる方は、早めに歯科医院を受診し、歯周病のリスクをチェックしてもらいましょう。
山梨県甲府市の山浦歯科医院では、歯周病専門医が歯周病の予防から治療、メインテナンスまでトータルでサポートいたします。
特に歯周治療においては、最新の診断支援アプリ「Perio DX」を導入し、初期段階の炎症も正確に検出し、迅速な対応を行っています。
患者様一人ひとりの状態に合わせた最適な治療プランをご提案しておりますので、歯ぐきや口元に違和感を覚えた際は、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個々の症状や治療については必ず歯科医師に相談し、適切な診断や治療を受けてください。