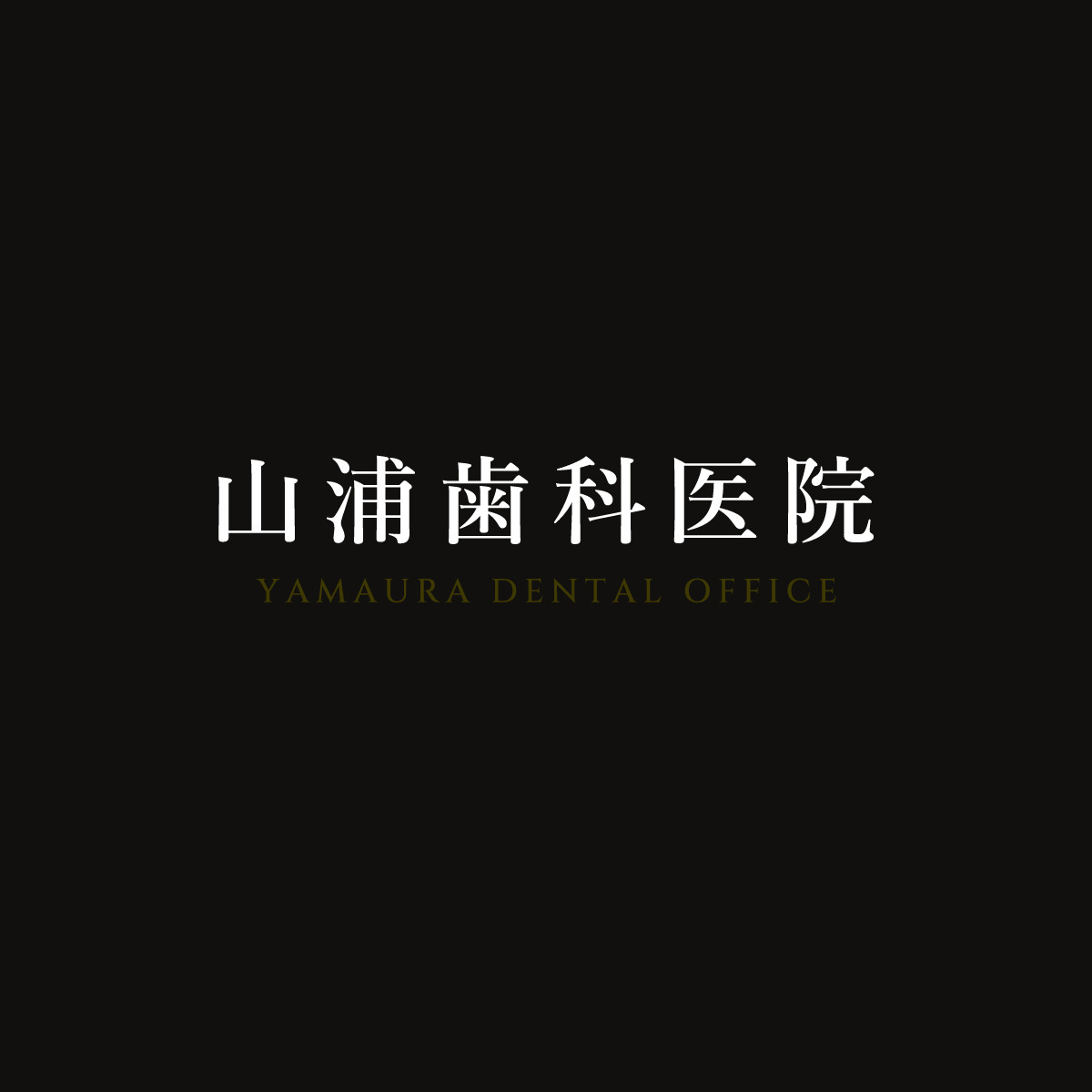歯茎が下がる原因と下がった歯茎を戻す治療方法を現役歯科医師が解説
- 山浦 泰明

- 2025年3月24日
- 読了時間: 8分
更新日:2025年11月20日

歯や歯茎の健康意識が高まっている中で、「歯茎が下がってしまった」「歯が長く見える気がする」といったお悩みを抱える方が年々増えています。
実はこれらのお悩みは、「歯肉退縮」が原因となっていることが多く、歯茎が下がると見た目に影響が出るだけでなく、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
この記事では、山梨県甲府市の山浦歯科医院の院長が、現役歯科医師の立場から歯茎が下がる主な原因や下がった歯茎を戻すための治療方法、日常でのケアのポイントについてわかりやすく解説します。
歯茎が下がる(歯肉退縮)とは?
歯茎が下がる(歯肉退縮)とは、本来歯を支えている歯茎が減ってしまい、徐々に歯根側へと後退してしまう状態を指します。
歯肉退縮の状態では、
歯が長く見える、歯と歯の間に隙間ができる
冷たいものや熱いものがしみる(知覚過敏の症状)
歯周病や虫歯にかかりやすくなる
歯がグラグラする
口臭が発生しやすくなる
など、見た目が悪くなってしまうことに加えて、生活面、健康面においても様々なリスクが発生します。
歯茎の後退が軽度の場合、症状を自覚しづらいこともありますが、進行すると歯の寿命を左右する重要な問題へと発展する可能性がるため、早めに対処することがおすすめです。
歯茎が下がる5つの原因とは?
歯茎が下がる原因は多岐にわたりますが、主な原因は以下の5つです。
歯周病の影響
不適切なブラッシング
加齢による歯茎の退縮
歯ぎしりや食いしばり
不適切な歯科治療
1.歯周病の影響
歯周病は、日本人成人の多くが罹患しているとされる国民病ともいわれる疾患です。
歯周病が進行すると、歯茎が炎症を起こし歯周ポケットが深くなり、歯を支える歯槽骨(しそうこつ)が徐々に溶けていくため、その結果として歯肉が退縮し、歯が長く見えることがあります。
軽度の段階ではほとんど自覚症状がありませんが、歯周病が原因で歯茎が下がるケースは非常に多いです。
2.不適切なブラッシング
歯ブラシを強い力でゴシゴシと横に動かす、硬い毛先の歯ブラシを使い続けるなどの不適切なブラッシングは、歯茎を傷つける原因となります。
特に歯と歯茎の境目部分の歯頸部はデリケートなので、過度の力や間違った角度でブラッシングすると、歯茎が物理的に強い刺激を受け、炎症を起こしやすくなるため注意が必要です。
3.加齢による歯茎の退縮
年齢を重ねるにつれ、全身の皮膚や筋肉と同様に歯茎も徐々に変化していくため、年をとればとるほど歯肉は薄くなりやすく、摩擦や刺激に対して弱くなる傾向があります。
ただし、加齢そのものがすぐに大きな退縮を引き起こすわけではなく、他の要因が重なって進行することがほとんどです。
4.歯ぎしりや食いしばり
就寝中の歯ぎしりや、日中の食いしばりの習慣は、歯や歯茎、顎関節に過剰な負荷をかけます。
歯ぎしりや食いしばりによって歯が揺さぶられると、歯周組織に負担がかかり、次第に歯茎が退縮する場合があります。
また、歯ぎしりや食いしばりの力によって、歯と歯茎の境目にくさび状の欠損(歯のえぐれ)を生じることもあります。
5. 不適切な歯科治療
過去に歯科医院で実施した治療の中で、適合の悪い被せ物(クラウン)やブリッジ、設計不良なインプラントなどがあると、その周囲に歯垢(プラーク)がたまりやすくなり、歯茎や歯槽骨にダメージを与えます。
その結果として歯茎の後退を起こす可能性があります。
また、歯列矯正については適切な治療が行われていても歯茎が下がることがあります。
下がった歯茎は戻る?下がった歯茎を戻す治療方法
結論から言うと、一度下がった歯茎は戻すことが難しく、今以上に進行させないことが重要になります。
ここでは歯周病治療を中心に、代表的な治療法をいくつか紹介します。
スケーリング・ルートプレーニング
歯周病が原因で歯茎が下がっている場合、スケーリングとルートプレーニングで、まず歯周ポケット内部に潜む歯石を取り除きます。
スケーリングは歯石やプラークを専用の器具や超音波スケーラーで除去する処置で、ルートプレーニング:は歯石除去後、歯根面を滑らかに整える処置で、これにより歯周病の進行を抑制し、歯茎が炎症から回復しやすい環境を整えます。
フラップ手術(FOP・歯肉剥離掻把術)
重度の歯周病で深い歯周ポケットが形成されている場合、感染源を徹底的に除去し、歯茎の健康回復を目指します。
主には歯肉剥離掻把術で歯周ポケット内部の炎症組織を除去し、歯肉の再付着を促したり、歯茎を一時的に切開してはがし、歯石や炎症組織を直接目視下で除去するフラップ手術などの外科的な処置が検討されます。
歯茎の移植
すでに大きく歯茎が下がってしまった場合、患者さんご自身の口蓋(上あごの内側など)から歯肉を採取して移植する歯肉移植術や、歯茎内部の結合組織のみを移植し、審美性と機能性の回復を図る結合組織移植術を検討します。
これらの手術によって、露出している歯根面を覆って、歯茎の厚みや保護を回復することが期待できますが、術後のケアや衛生管理が十分でないと再度歯茎が下がる恐れがあるため、定期的なメンテナンスが欠かせません。
再生療法(GTR法など)
GTR法(歯周組織再生誘導法)など、再生療法を利用した治療は、歯槽骨や歯周組織が再生しやすい環境をつくることで、歯の周囲組織を再生させることを目指します。
ただし、再生療法は適応症例が限られており、必ずしもすべての症例に当てはまるわけではありません。
歯科医師の判断のもとで、適切な治療計画を立てることが大切です。
かみ合わせの調整
歯ぎしりや食いしばり、かみ合わせの不良が歯茎後退の大きな要因となっている場合は、マウスピース(ナイトガード)や咬合調整(こうごうちょうせい)といった治療で力のバランスを整えます。
これにより、過度な負荷から歯茎や歯を守り、歯肉退縮を防止します。

自宅でできる歯茎ケアは?予防方法を解説
歯茎が下がってしまう原因を取り除き、症状の進行を抑えるためには、日々の丁寧なケアが欠かせません。
特に、自宅でのセルフケアを習慣化することで、歯茎や歯周組織を健康に保ちやすくなります。
ここでは、正しい歯磨きの方法やデンタルフロス・歯間ブラシの活用、食習慣や生活習慣の見直しなど、自宅で取り組める具体的な予防策について解説します。
正しい歯磨き
正しい歯磨きでは、まず歯ブラシを強く押しつけすぎないように注意し、軽い力で磨くことが大切です。
過度な圧力をかけると歯茎を傷つける原因になるため、できるだけ優しいタッチを心がけましょう。
次に、歯ブラシを歯と歯茎の境目に45度程度の角度で当てるようにすると、歯と歯茎が接する部分のプラークを効率よく除去できます。
さらに、ゴシゴシと大きく動かすのではなく、小刻みに動かすことで歯や歯茎への負担を減らしながら汚れを落としやすくなります。
歯ブラシの毛の硬さはやわらかめ~ふつうを選び、歯磨き粉も研磨剤が無いタイプにすると歯茎へのダメージを一層予防できます。
デンタルフロスや歯間ブラシの活用
歯と歯の間には歯ブラシの毛先が行き届きにくい部分が多いため、デンタルフロスや歯間ブラシを使って補助的にケアすることがおすすめです。
デンタルフロスは糸状のものを歯間に入れてプラークを取り除く方法で、隙間の小さい部分にも入り込みやすいのが特徴です。
一方、歯と歯の間にやや広いスペースがある方は歯間ブラシを使用すると、効率的に汚れを除去でき、特に歯茎が退縮して隙間が目立ちやすくなった部分では、歯間ブラシが効果を発揮しやすいです。
ただし、歯間ブラシのサイズが合わないと歯茎を傷つける恐れがありますので、歯科医院で自分に合ったサイズを相談するのが安心です。
食習慣の見直し
バランスの良い食事を心がけ、ビタミンやミネラルを十分に摂取すると、歯茎を含む歯周組織の健康維持を助けてくれます。
反対に、糖分を過剰に摂取すると虫歯や歯周病のリスクが高まるため、甘いおやつやジュースなどは摂りすぎに注意しましょう。
食後は歯磨きを徹底するとともに、なにかを食べた後は水を飲んで口内の汚れを早めに洗い流す習慣をつけると、歯茎や歯へのダメージを軽減できます。
ストレス・生活習慣の改善
トレスは免疫力の低下を招き、歯周病が進行しやすくなる要因とも言われています。
また、強いストレスによって歯ぎしりや食いしばりが起こると、歯茎や顎関節に負担がかかりやすくなります。
加えて、喫煙習慣がある場合はタバコの有害物質が歯茎の血行を妨げ、歯周組織の回復を遅らせる原因にもなります。
適度な運動や十分な睡眠を確保し、ストレスを軽減できるような趣味やリラックス法を取り入れるなど、全身の健康を考えた生活習慣の改善も歯茎ケアには重要です。
歯茎が下がってお悩みの方は山梨県甲府市の「山浦歯科医院」
山梨県甲府市の山浦歯科医院では、歯周治療(歯周病・インプラント治療)を中心とし、経験豊富な専門医・スタッフで世界基準の高精度の治療を実施しています。
当院では、患者さま一人ひとりに適した治療計画を立案するだけでなく、治療方針や費用、期間なども患者さまが理解しやすいよう丁寧にご説明しております。
甲府市周辺で歯茎や歯に関することでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個々の症状や治療については必ず歯科医師に相談し、適切な診断や治療を受けてください。