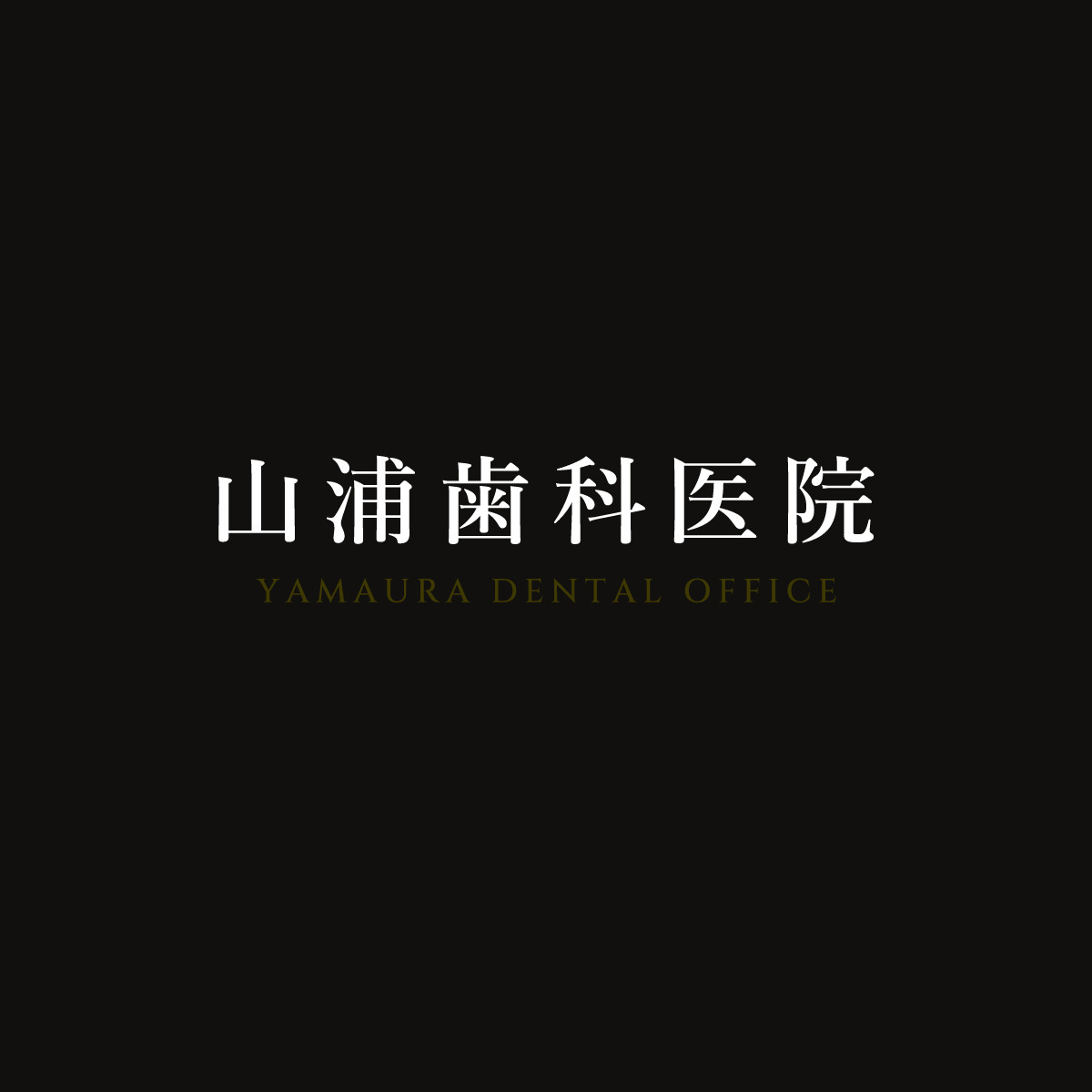虫歯の神経を抜くとどうなる?神経を抜く・抜かないの判断基準・神経を抜く治療について現役の歯科医師が解説。
- 山浦 泰明

- 9月1日
- 読了時間: 10分
更新日:11月20日

「虫歯が進行して神経を抜かなければならないかもしれない」と歯医者さんに言われて、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
歯の神経を抜くという処置は、日常生活ではあまり経験することのない治療であり、どのような影響があるのか心配になるのは当然のことです。
今回は、虫歯の神経を抜くとはどういうことなのか、どのような場合に必要になるのか、そして最新の神経を残す治療法について、山梨県甲府市の山浦歯科医院の院長が、現役歯科医師の立場からわかりやすく解説していきます。
歯の神経(歯髄)とは?その重要な役割
歯の神経について正しく理解することは、適切な治療選択を行う上で非常に重要です。
ですが多くの患者様が「歯の神経」という言葉は聞いたことがあっても、その具体的な働きや重要性については詳しく知らないのが現状です。
ここでは、まず歯の神経の基本的な構造から機能を分かりやすく解説します。
歯髄の構造と機能
歯の神経と呼ばれているものは、正確には「歯髄(しずい)」といいます。
歯髄は歯の中心部にある軟らかい組織で、神経だけでなく血管やリンパ管なども含まれています。
歯の構造は外側から順に、エナメル質、象牙質、そして中心部に歯髄腔があり、その中に歯髄が入っていて、歯髄には主に以下の重要な役割があります。
感覚を伝える機能:強い温度刺激(冷たい・熱い)などの刺激を脳に伝える
栄養供給機能:血管を通じて歯に栄養などを供給する
防御機能:細菌の侵入に対して免疫細胞を送り込み、歯を守る
歯の形成:若い時期には象牙質を作り出し、歯を成長させる
歯の神経が大切な理由
歯髄があることで、歯は生きた組織として機能を保つことができます。
虫歯ができても初期段階で「しみる」、「痛い」などの何かしらの症状を感じることで、早期発見・早期治療につながります。
また、歯髄から栄養が供給されることで、歯の強度や弾力性が保たれ、噛む力に耐えることができます。
神経を抜くとどうなる?歯の神経を抜くメリット
では、神経を抜くとどうなってしまうのでしょうか。
神経を抜く治療にはメリット・デメリットがありますが、神経を抜く治療のメリットは以下のようなものがあります。
1. 痛みから解放される
虫歯による激しい痛みから解放され、日常生活を取り戻すことができます。
痛みの原因となっている炎症を起こした神経を取り除くことで、根本的な解決が図れます。
2. 歯を残すことができる
神経を抜いても、適切な治療を行えば歯そのものは残すことができます。
抜歯を回避し、自分の歯で噛み続けることが可能になります。
3. 感染の拡大を防げる
細菌感染が顎の骨や周囲の組織に広がるのを防ぐことができます。
放置すると全身への影響も懸念されるため、早期の処置が重要です。
歯の神経を抜くデメリット
一方で神経を抜くと、以下のようなデメリットも出てきます。
1. 歯がもろくなる
血管からの栄養供給が絶たれるため、歯は枯れ木のような状態になります。
水分が失われて脆くなり、特に硬いものを噛んだときに歯が割れるリスクが高まります。
統計的には、神経を抜いた歯は10~30年後に歯根破折を起こす可能性があるとされています。
2. 虫歯の再発に気づきにくくなる
痛みを感じなくなるため、新たな虫歯ができても自覚症状がありません。
そのため、気づいたときには虫歯が大きく進行していることもあります。
3. 歯の変色が起こる
神経を抜いた歯は、時間の経過とともに黒ずんだり茶色く変色したりすることがあります。
特に前歯の場合は見た目の問題が生じることがあります。
4. 再治療が必要になることがある
根管治療の成功率は100%ではなく、細菌の取り残しなどにより再治療が必要になることがあります。
特に日本の保険診療での治療では治療方法や材料に制限があるため、成功率は30%未満といわれています。
歯の神経を抜く・抜かないの判断は?危ないケースを紹介
歯科治療において最も重要な判断の一つが、歯の神経を保存するか除去するかの決定です。
この判断は患者様の現在の症状、歯髄の状態、将来的な予後など、多くの要因を総合的に評価して行われます。
基本的には可能な限り神経を保存し、やむを得ない場合のみ除去することが現代歯科医学の方針となっていますが、以下のような症状がある場合、神経を抜く治療(抜髄)が必要になる可能性があります。
1. 何もしていなくても歯がズキズキ痛む
虫歯が歯髄まで達すると、歯髄が炎症を起こし(歯髄炎)、激しい自発痛が生じます。
この痛みは痛み止めを飲んでも一時的にしか和らがず、夜も眠れないほどの強い痛みになることがあります。
2. 冷たいもの・温かいものがしみて痛みが長く続く
知覚過敏の場合は一瞬しみる程度ですが、神経まで虫歯が達している場合は、冷たいものや温かいものを口にした後、5秒以上痛みが続きます。
特に温かいものがしみる場合は、虫歯がかなり進行している証拠です。
3. 噛むと激痛が走る
虫歯が神経全体に広がると、歯に少しでも圧力がかかると激しい痛みを感じるようになります。
食事はもちろん、歯が触れ合うだけでも痛むため、日常生活に大きな支障をきたします。
4. 歯茎が腫れて膿が出る
虫歯菌の感染が歯の根の先まで広がると、顎の骨の中に膿がたまり、歯茎が腫れたり、歯茎から膿が出たりすることがあります。
頬やリンパ節まで腫れることもあり、この状態では神経はすでに壊死している可能性が高いです。
5. 歯の色が変色している
歯が黄色や灰色、黒っぽく変色している場合、神経が死んでしまっている(失活)可能性があります。
外傷で歯を強く打った後などにも起こることがあります。
虫歯の進行度による分類(C1~C4)
虫歯の進行度は、専門的にはC1からC4の4段階に分類されます。
この分類は、虫歯がどの程度歯の内部まで進行しているかを示す重要な指標で、歯科医師は虫歯の進行度も確認しながら治療方針を決定します。
進行度 | 状態 | 主な症状 | 神経を抜く必要性 |
|---|---|---|---|
C1(エナメル質う蝕) | 歯の表面(エナメル質)のみの虫歯。深さ2~2.5mm程度 | ・ほとんど痛みなし・見た目の変化(白や茶色の斑点) | 不要 |
C2(象牙質う蝕) | エナメル質を突破し、象牙質まで達した虫歯 | ・冷たいもの、甘いものがしみる・普段は痛みなし | 不要(深い場合は要検討) |
C3(歯髄炎) | 虫歯が歯髄(神経)まで達した状態 | ・何もしなくてもズキズキ痛む・夜間に痛みが増強・温かいものもしみる | 多くの場合必要 |
C4(残根状態) | 歯冠部が崩壊し、歯根のみ残存。神経は壊死 | ・痛みを感じないことも・根の先に膿が溜まると激痛・歯茎の腫れ | 必要(抜歯の可能性も) |
C1:エナメル質う蝕
歯の最も外側にあるエナメル質に限局した虫歯です。
厚さ約2~2.5mmのエナメル質部分のみが侵されている状態で、痛みを感じることはほとんどありません。
この段階では、虫歯を削って詰め物をする簡単な治療で済み、神経を抜く必要はありません。
C2:象牙質う蝕
エナメル質を突破し、その内側にある象牙質まで虫歯が進行した状態です。
冷たいものや甘いものを食べた時に歯がしみることがありますが、普段は痛みを感じることは少ないでしょう。
この段階でも、適切な治療を行えば神経を残すことが可能です。
C3:歯髄炎
虫歯が歯髄(神経)まで達している状態です。何もしていない時でもズキズキとした痛みがあり、夜間に痛みが増強して眠れないこともあります。
この段階になると、多くの場合で神経を抜く治療(抜髄)が必要となります。
C4:歯根だけが残った状態
虫歯が進行して歯冠部(歯の頭の部分)が崩壊し、歯根だけが残った状態です。
神経はすでに壊死していることが多く、痛みを感じないこともありますが、根の先に膿が溜まることで激しい痛みが生じる場合があります。
虫歯が神経に到達した場合の治療は「根管治療」
虫歯が神経まで達してしまった場合、「根管治療」という治療を実施します。
根管治療は、虫歯が神経まで達した場合や、神経が壊死した場合に行う治療で、歯の内部にある神経や血管を除去し、根管内を清掃・消毒した後、薬剤で密封する一連の治療を指します。
この治療により、抜歯を回避し、自分の歯を残すことが可能になります。
根管治療の実際の流れは以下の動画をご覧ください。
歯の神経を残す治療法
また、現代では歯科医療の進歩により、従来は神経を抜くしかなかった深い虫歯でも、神経を残せる可能性が高くなっています。
すべてのケースで可能というわけではありませんが、当院でも実施している神経保存治療の選択肢について詳しくご説明します。
断髄法(部分的歯髄除去)
虫歯が歯髄に達していても、感染が限局的な場合には感染部分のみを除去し、健康な歯髄を保存することが可能です。
主に若年者の歯や、外傷により歯髄が露出した場合に適応されます。
VPT(歯髄温存療法)
VPT(Vital Pulp Therapy)は、日本語で歯髄温存療法と呼ばれる治療法です。
従来であれば神経を全て取らなければならなかった症例でも、感染した部分のみを除去し、健康な歯髄を残すことができる画期的な治療法です。
近年、MTAセメントやバイオセラミックセメントといった生体親和性の高い材料が開発されたことで、この治療の成功率が大幅に向上しました。
当院でも、適応症例には積極的にVPTを行い、患者様の大切な歯の神経を守る努力をしています。
山浦歯科医院の根管治療における最新の技術と設備
根管治療の成功率は、歯髄保存に関する知識、エビデンスに基づく医療、使用する機器や材料、そして歯科医師の技術によって大きく左右されます。
従来の治療では、肉眼や拡大鏡での限られた視野で行われていましたが、現在ではマイクロスコープやCTなどの最新機器を用いることで、より精、高精度で確実な治療が可能となっています。
また、ニッケルチタンファイルなどの新しい器具の登場により、複雑な根管形態にも対応できるようになりました。
当院では、これらの最新技術を積極的に導入し、患者様により質の高い根管治療を提供しています。
マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)の活用
根管治療の成功率を高めるため、当院ではマイクロスコープを使用した精密治療を行っています。
マイクロスコープを使用することで肉眼では見えない細かい部分まで確認できるため、精密な処置が行えるほか、治療の様子を録画することも可能です。
ニッケルチタンファイルの使用
従来のステンレス製ファイルに比べ、柔軟性が高く、複雑な根管形態にも対応できます。
これにより、根管内の清掃効率が向上し、治療時間の短縮にもつながります。
3次元的な診断(歯科用CT)
通常のレントゲンでは分からない根管の複雑な形態や、根の先の病変の大きさを正確に把握できます。
これにより、より適切な治療計画を立てることが可能になります。
根管治療・再治療なら山梨県甲府市の「山浦歯科医院」
歯の神経を抜く・抜かないの判断は、虫歯の進行度、症状、歯髄の状態などを総合的に評価して決定されます。
可能な限り神経を残すことが歯の長期的な健康には重要ですが、進行した虫歯では神経を抜く治療が必要になることもあります。
山梨県の山浦歯科医院では、全ての根管治療においてマイクロスコープを(歯科用顕微鏡)を使用し、肉眼では見えない細部まで確認しながら精密な治療・再治療を行っています。
また、最新のVPT(歯髄温存療法)により、従来なら神経を抜くしかなかった症例でも、神経を残せる可能性が広がっています。
山浦歯科医院では、最新の設備と技術を用いて、患者様の大切な歯を守るための最善の治療を提供しておりますので、
「神経を抜く必要があるかもしれない」と不安を感じている方、セカンドオピニオンをご希望の方も、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個々の症状や治療については必ず歯科医師に相談し、適切な診断や治療を受けてください。